――恋に落ちたのが何時だったのか、ヒナタは覚えていない。
初めて会ったその時、男なのに黒髪を長く伸ばした姿に眼を丸くした、その時だろうか。
それともその髪の下の、若々しい顔が眉目秀麗の形容そのままに端正であったことに気付いた、その時だろうか。
ただ、気付けば自分はもう恋をしていた。

別に、ヒナタが彼に恋をして、一緒にいられたらと心ひそかに願ったから、というばかりではなかろうが。その青年は、ヒナタたった一人きりだった古い家に、来てくれた。
一匹の猫と一緒に。
「ネジ!」
引越しの荷運びの手伝いに来てくれた、リーが焦ったように上げた声にネジは振り返った。
「何だ」
「ナルトくんが庭に出ちゃいましたっ」
「…ああ」
「ああ、って…いいんですか?その…」
「ナルトの奴はここの庭が気に入っているようだからな」
「えー心配じゃない?」
手伝いその2であるところのテンテンが騒ぎを聞きつけたか、やって来て口を挟む。
「慣れるまではあんまり外に出したりしない方がいいらしいよ?」
ほら、猫って家につくって言うじゃない。
わやわやとかしましい屋内とかわって静かな庭に、いたヒナタのもとへ明るい黄色の毛並みの猫が近づいてきた。
ようやっと子猫でなくなったばかりの、まだまだやんちゃだろう若猫。
「…なると、…くん?」
なのに妙にものを分かっている風で、ヒナタを見上げてにあ、と鳴く。彼女をやたら恐れたり嫌ったり威嚇したりはしてこなかった。
それが嬉しく、微笑った。
「よろしくね」
言えばまた、にあ、と穏やかに鳴かれ、ヒナタはいっぺんでナルトを好きになった。
だから、ナルトの飼い主であるネジをも好いた、かは判らないのだけれど。
ただ、同じ家にあの人がいる、と思うだけで胸が躍った。幸福だ、と感じるようになった。
自分が彼の存在にどれだけの幸福を感じているか、せめてもそれを伝えたく思ったが、声すらかけられずに遠くから姿を眼で追うが関の山だった。
それでも幸せはいささかも減ずることがなかったのだ。
この家でネジは。あまり出歩かず在宅して、持ち込んだパソコンの画面の前に座っていることが多かった。
何をしているのかヒナタにはまるで判らない。最初はただ単純にそれを喜んでいた。彼が家にいてくれる間は、ヒナタにも彼を見る機会があるので。
だがそのうち、彼は娯楽や一時の情報収集のためにではなく、どうも何かの仕事か勉強かをするために機械の前に座るらしい、というのがおぼろげながら判ってきた。具体的に何をしているのかは判らないけれど。
あんまりじろじろ見られているのも気が散るだろうから(ネジは時々気配に勘付くのか振り向くことがある)、そういう時ヒナタは大抵庭へ出る。
この家の庭には花が多い。
春には椿、海棠、沈丁花。
夏が来て牡丹、芍薬、山紫陽花。
四季折々に、花々の咲くこの庭を、ヒナタは愛していた。
ああ、そうだ。初めてこの庭を見たネジが、俺は風流には興味がないが、と前置きながらも
「花が多いのは、いいな」
と言った時、誇らしいとさえ言えるような気持ちになった、恋はその時に始まったのかもしれない。
自分で植えた花がどれだか、ネジに教えられたらと望むけれど、幼い手で植えた花を、ヒナタ自身よく覚えていない。
花びらをそっと指先で掠めて、ふとヒナタは母屋を振り返った、――そしたらそこにネジがいた。
テラスの手すりに座って。隣にナルトを置いて。夕涼みでもするかのように庭を。こちらを。
――見ている。
眼が合う。ほんの少し。鼓動が高鳴るような気さえする。彼は、ごく薄くだが、笑っている。穏やかに。
ヒナタは何も言えず、ただぎこちなく微笑み返す。
夕暮れ時には、たまにこういうことがある。
黄昏時には。
その幸運に感謝して、でも、これが夕まぐれの瞬きではなく、永遠に続くのであればと願わずにはいられない。
庭で物凄い吼え声と唸り声があがって、ネジは何事かとパソコン画面から顔を上げた。
犬の吼え声と猫の唸り声。
慌ててテラスまで走り出ると、庭の小道の真ん中、ナルトが常の3倍くらいに膨れ上がって、シャーッと威嚇の声を上げている。目の前の、犬に対して。
「コラっ!!」
咄嗟に大声を上げると、紛れ込んできた犬はネジに対しても低く唸ったが、しっ、と追い払う仕草を見せるとそれ以上は粘らず身を翻して走り去った。
その背中に、へのへのもへじの縫い取り。首輪もしていたし、どこかで見たような犬だとは思ったが、それではっきりした。へのへのもへじの縫い取りの入った服を着せられているなら、近所のはたけ家の飼い犬に間違いない。あの家はやたらに犬を飼っている。
「まったく…」
憤慨しながら、少し妙だな、とネジは思った。はたけ家の飼い犬はいずれも、風邪だ花粉症だアレルギー性鼻炎だと聞くたび異なる理由でマスクを外さない胡散臭い男が飼い主ではあるが、躾の非常に行き届いた、ちょっと行き届きすぎた、犬だ。軍用犬というのはもしかしてああいう感じなのかもしれない、と印象を抱いた覚えさえある。
第一、あそこの家は猫も飼っていた、たしか。だから猫には慣れているはずだし、やたらその猫に懐いているナルトはちょくちょく向こうに出かけているので、喧嘩を売り買いするような仲とも思えない。
今回の報告がてら一度向こうに聞きに行くべきか、と考え、さしあたってネジは
「お前も尻尾を戻せ」
ナルトに言った。逆立てた体の毛はもう戻っていたが、尻尾はまだ膨れ上がったままで、色のせいもあって床拭きモップのようだった。
まだ憤懣やるかたない、といった調子でウルルルル、と唸っているのを抱き上げて撫でてやって、ようやっとしぼんでいく。
改めて庭を見れば、花が大分ダメになり、犬の習性と言えば仕方ないのだろうが、いくつか穴が掘られている。うち一つは随分深いようだった。
これはやはり一度、文句を言いに行くべきか。
思って穴を覗き込み、ネジは、土の中に白っぽい何かが埋もれているのを見つけた。
「…?」
気になったのは何故だろうか。
その白っぽいものが、どうも一つではないらしいのが見えたからだろうか。
身をかがめて指先で軽くその辺りの土を穿ってみて、はっきりと露になったものに流石のネジも絶句した。
「ネジ!聞きましたよ!!」
「リー。テンテン」
「庭から人の骨が出てきたんですって!?」
騒々しく扉を開けて、飛び込んできたリーとテンテンが叫ぶ。
「ああ。ようやっと警察だの何だのが帰って行ったところだ」
うぇー、と露骨に顔をしかめたのはテンテンで、リーはどちらかというと痛ましそうな顔をした。
「災難でしたね、ネジ」
「ここ、古い家だし、昔きっと猟奇殺人事件とかあったのよ!」
純粋に心配しているらしいリーに対して、テンテンはワイドショーノリが強い。それでも
「あ、これ差し入れ。パンにしといたわ、すぐ食べられるし」
サンジェルマン好きだったでしょ、と細やかな心配りを見せてくれる。
「ナルトにはモンプチね」
おいでー、と猫に誘いをかける相方の傍ら、
「で、誰の骨だったんですか?」
リーは真面目に気にしているようだ。
「それは今から警察が調べるだろう。持って行ったばかりだ、まだ」
「それじゃ男性か女性かさえも判らないんですね…」
ちょっと怖そうに呟くリーに、ネジは
「女だ」
返した。
あんまりきっぱりと言うので、リーもテンテンもきょとんとして
「「なんで?」ですか?」
と断言の理由を問うてくる。
「何度か見たからな」
「「…“見た”?」」
きれいなユニゾンで聞き返した二人は、互いに顔を見合わせそしてネジに顔をまた向ける、一連の動作の全てが予め打ち合わせでもしていたかのように揃っている。
相変わらず息の合ったコンビだなあ、とネジは感心する。
「ネジ、それは――」
「いやっ近寄らないで!」
真剣な顔をして問いただしてこようとするリーに、芝居がかった悲鳴で身を退くテンテン。
「別にそう恐ろしいものを見たわけではない」
一人泰然としているネジ。予定調和の演劇を演じている感がなくもない。付き合いが長いから、この三人でいると自然にそれぞれの役割を演じてしまう。
「判ったわ!夜な夜な美女が通ってきたのね!」
牡丹燈籠みたいに!
と、眼をきらっきらさせながらワイドショーノリを復活させるテンテン、
「テンテン…女性がそういう話をするのは、あんまり…」
この程度で頬を染めて、たしなめに入るリー。
まったく、と笑って、ネジは
「そういうのでもなかったな」
真面目に説明を試みる。リーほどじゃないと思っているが、ネジは生来生真面目だ。
「最初は時々、誰かの気配を感じていただけだったんだが」
話しながら丁寧に記憶を選り分けていく。
「――そうだな、たとえば、黄昏時に。ナルトとテラスに出て庭を眺めていたりすると――」
庭を見ている分には何も見えないんだが、ナルトがな。
「じっと庭の方を見ているんだ。その視線の先を追っていくと彼女がいる」
長い袂をたゆたゆと遊ばせて。
「尋常の人間ではないことは判るが、怖くはない。儚い幻のようで――」
彼女は結局誰だったのだろうな、とネジは思った。
もう戻っては来ないのだろうか。
宵闇せまる花のそば、長い黒髪を滑らせて、生きている人のようにネジの視線に振り返り、はにかむように笑った、あの少女は。
この綺麗な夢はいつまで続いてくれるのだろう、と眺めながら思った自分は、きっと、彼女に、恋をしていた。
あとがき
Wパロディ:波津彬子「花の庭にて」(『秋霖の忌』白泉社文庫、2001 所収)
(UP 09/12/29)
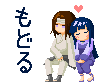
 ←作者の光村真知さまに一言〜長文メッセージをどうぞ!
←作者の光村真知さまに一言〜長文メッセージをどうぞ!
